神仏霊場のロゴをクリックすれば表紙に、奈良・鎮護の道をクリックすれば奈良霊場の目次に戻ります。
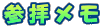 |
|
二月堂は1180年(治承4年)平重衡の兵火、1567年(永禄10年)三好三人衆と松永久秀の戦いの2回の戦火には焼け残ったが、1667年(寛文7年)お水取りの最中に失火で焼失し、2年後に再建されたのが現在の建物で、2005年(平成17年)国宝に指定された
。 |

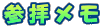 |
|
二月堂は1180年(治承4年)平重衡の兵火、1567年(永禄10年)三好三人衆と松永久秀の戦いの2回の戦火には焼け残ったが、1667年(寛文7年)お水取りの最中に失火で焼失し、2年後に再建されたのが現在の建物で、2005年(平成17年)国宝に指定された
。 |
