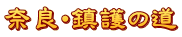| [率川神社所在地]:奈良市本子守町 JR奈良駅よりは三条通りを東へ、徒歩約5分 観光センター角を北へ、やすらぎの道を南へ、すぐ 近鉄奈良駅よりはやすらぎの道を南へ、徒歩約7分 |
  |
| [参考資料:率川神社パンフレット『率川神社縁起』] |
|
『率川神社縁起』の「ご由緒」によれば、「593年(推古天皇元年)大三輪君白堤(オオミワノキミシラツツミ)が勅命により創祀した奈良市最古の神社である。祭神の媛蹈鞴五十鈴姫命(ヒメタタライスズヒメノミコト)は神武天皇の皇后で、三輪神社の祭神大物主大神(狭井大神)の子供にあたり、『延喜式』にには率川坐大神御子神社の名で記載されている」。 |
 |
 |
 |
| ならやま大通りに面した率川神社正面入口。注連柱と鳥居が前後して建てられている。 | 正面入り口の鳥居。いわゆる「一の鳥居」か。 | 拝殿。入口は鍵が掛かっており、中には入ることはできなかった。 |
 |
 |
 |
| 拝殿の内部。拝殿の外から、ガラス越しに本殿を拝んだ。 | 本殿を塀の格子越しに写した。上の写真は左側から狭井大神(五十鈴姫命の父神)、媛蹈韛五十鈴姫命、玉櫛姫命 (五十鈴姫命の母神)、右側の写真は右側から玉櫛姫命、媛蹈韛五十鈴姫命、狭井大神。各々本殿は一間春日造、 檜皮葺で、奈良県の有形文化財に指定されている。 |
|
 |
 |
 |
| 境内摂社・末社が祀られている一角。鳥居の右側に建っ ている灯篭は摂社・率川阿波神社が祀られていた旧地 より移した。「享和三年(1803年)阿波社」の銘がある。 |
摂社・率川阿波神社。この神社は772年(宝亀2年) 大納言藤原是公建立と伝えられ、『延喜式』に載る古社で、事代主神を祀る。旧跡は奈良市西城戸町にあり、1920年(大正9年)当地に鎮座。 |
摂社・率川阿波神社を中央に、末社・春日社(右)と末社・住吉社(左)が並んで祀られている。 |
 |
 |
 |
| 本社・大神神社を望む遥拝所。高さ約2mの石製の衝立には平山郁夫画伯作の「神の山 三輪山の月」の陶版画はめ込まれている。 | 境内に建つ万葉歌碑。「はね蘰(かづら) 今する妹を うら若み いざ率川の 音の清(さや)けさ」 作者不詳 『万葉集 巻七』。 万葉時代は率川は現在のように「いさがわ」ではなく、いざかわ」と呼ばれていたとのことであり、この歌はいざ(さあ)という言葉とかけて、詠まれている。 |
カエルの姿によく似た「カエル石」。案内板によれば、「カエル」という言葉から、「お金がかえる」「幸せがかえる」「若かえる」 「無事かえる」などにつながり、縁起が良いとされ、健康回復・旅行安全などを願って、参拝者がこの石を撫でることから「撫で蛙」とも呼ばれ、親しまれているとのこと。 |
|
大三輪君白堤をネットで検索すると、「白堤は『古事記』用明天皇3年5月条(586年)に、用明天皇から皇位を奪おうとした穴穂部皇子へ、先帝敏達天皇の殯宮を警備していた寵臣三輪逆(ミワノサカウ)の居場所を密告して、その殺害に協力した人物。」との記述が見られたが、『デジタル版 日本人名大辞典+Plus』には『古事記』に記載されている事柄に加え、「『大三輪三社鎮座次第』によれば、(白堤は)推古天皇のとき、勅により春日三枝神社(現率川神社)をたて、媛蹈韛五十鈴媛命と大物主神を祀った。」との記述があり、『率川神社縁起』と同一の記載が見られた。 |