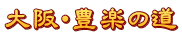神仏霊場のロゴをクリックすれば表紙に、大阪・豊楽の道をクリックすれば大阪霊場の目次に戻ります。
| [参考資料:境内案内板] |
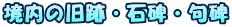 |
 |
 |
 |
| 五所御前(東正面)。神功皇后が住吉三神を祀るための 土地を求めたとき、この地の杉の木に白サギが3羽止まったのを見て、この地に奉祀した伝わる。 |
五所御前(西側)。石の玉垣のなかにある砂利の中に「五・大・力」と書かれた小石が混ざっており、これを集めてお守りにすると心願成就するとのことで、探した結果確保できた(右の写真)。大きさは石の下の白枡は一辺が1㎝。 | |
 |
 |
 |
| 元神宮寺跡。当寺は788年(天平宝字2年)創建と伝えられ、津守寺(廃寺)・荘厳浄土寺とともに住吉の三大寺 に数えられていた。明治初年の神仏分離令により廃絶。 江戸時代には仏堂8宇・僧坊10余を規模を有した。 |
源頼朝の寵愛を受けた丹後局がここで薩摩藩島津氏の始祖・島津忠久を出産した場所と伝えられる。 | |
 |
 |
 |
| 住吉行宮跡。住吉大社から南へ約300m(住吉区墨江2丁目)。南北朝時代、後村上天皇は1352年(正平7年)、奈良・吉野から住吉大社神主津守氏の邸内にあったここ正印殿に移り、行宮とした。後村上天皇が8年、長慶天皇が1年、合計約9年間行宮であった。国史跡。 | 大海神社境内の「玉の井」井戸。この井戸は龍宮伝説の海幸彦が海神より授かった潮満珠を沈めた井戸と伝える。 | 一寸法師伝説発祥の地。室町後期に成立した『御伽草紙』には、難波の老夫婦が住吉明神から授かった背丈1寸の一寸法師が、「お椀の舟に箸の櫂」で京に上り、鬼退治など大活躍をする話が載っているが、種貸社に置かれたあったお碗は、一寸法師でなくとも大の大人が十分に乗れる大きさであった。 |
| 住吉の三名花 住吉大社には古代・中世以来の歴史と伝統を伝える「卯の花苑」「浅沢の杜若」「車返しの桜」という名花があるが、訪問した時期がいずれも時季外れだった。 | ||
 |
 |
 |
| 浅沢の杜若。万葉集にも「住吉の 浅沢小野の杜若 衣に摺り付け 着む日知らずも」と詠まれているほど歴史は古い。昭和に入って「忘水」と称された浅沢の清水も枯れ、杜若に変わって明治神宮の花菖蒲が移植されていたが、1997年(平成9年)細江川改修の一環として浅沢に新しい水脈を加え、各地の原種の杜若を集め、復活した。 | 車返しの桜。後醍醐天皇が住吉大社に行幸の折、この付近にあった慈恩寺(津守家の菩提所。明治初年に廃寺)の桜があまりにも見事であったので車を引き返らせた故事があり、それを偲んで1999年(平成11年)に植えられた。 | 卯の花苑。住吉大社がこの地に鎮座したのが、神功皇后摂政11年卯の歳・卯の月・卯の日と伝え、「卯の葉神事」重要な神事となっている。「卯の花苑」は1986年(昭和61年)開苑。現存する日本のほぼ全品種の卯の花を移植してあるとのこと。 右手に後鳥羽院皇子光台院親王の歌碑「すみよしの ゆふしでなびく 松風にうらなみしろく かくるうのはな」が建つ。 |
| 歌碑・句碑・文学碑 | ||
 |
 |
 |
| 古代船を象った万葉歌碑。 遣唐使に餞する歌「住吉に斎く祝が神言と 行くとも来とも船は早けむ」多治比真人土作。 長皇子に進むる歌「草枕旅行く君と知らませば 岸の黄土ににほはさましを」清江娘児。 |
西鶴句碑。西鶴自筆から採られており、達筆すぎて読めない。 | 大海神社境内に建つ蜀山人歌碑。太田南浦は大坂在勤中、6度住吉大社を訪れているが、この碑は大坂の狂歌仲間が建立。12年前に取った写真に比べ、風化が進んでおり、上の部分が剥がれ落ちている。 |
 |
 |
|
| 生田南水句碑。「長閑さや岸の姫松忘れ貝」。 裏面の碑文によると南水の娘で日本画家の生田花朝が建立。花朝の師である菅楯彦が揮毫した。 |
川端康成文学碑。 川端康成『反り橋』より 「反り橋は上るよりも おりる方がこはいです 私は母に抱かれておりました」 |
|