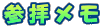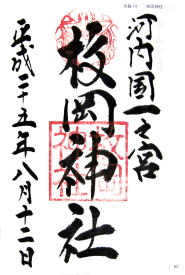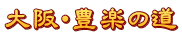|
 |
 |
| 近鉄奈良線「枚岡駅」の改札を出たところに建つ1853年(嘉永6年)の再建の大きな石碑。「当国一の宮 元春日平岡大社 右なら」と刻まれている。 |
近鉄枚岡駅の改札を出て、階段を登ると注連柱と注連縄が目に入る。両側の石柱には、「神事宗源」「天孫輔弼」が
彫られている。1922年(大正11年)に奉納された。 |
東西の参道を南北に横断する道路に建つ石鳥居。1940年(昭和15年)皇紀2600年を記念して建てられた。 |
 |
 |
 |
| 摂社若宮社。天押雲根命を祀る。1887年(明治20年)に改築され、現在に至っている。 |
末社天神地祇社。天津神・国津神を祀る。1872年(明治5年)にもと境内にあった19社と近郡の村々の氏神13社が合祀されている。 |
創紀2670年(皇紀2667年)に当たる2007年(平成19年)に整備された巽参道(摂末社参道)。 |
 |
 |
 |
| 拝殿への階段の登り口の左右に神鹿の石像がある。現地の案内板には「祭神の武甕槌命が神鹿に乗って旅立った故事(鹿島立)に因む。1846年(弘化3年)名工
日下小平次の作」とあったが、この神鹿以外の作品についての記載はなかった。 |
参道から広場に入ったところの左右2カ所に建つ巨大な石灯篭。1907年(明治40年)の奉納。 |
 |
 |
 |
ご神木「槇柏」。直径2.1m、周囲6.5m。650年(白雉元年)現在地に社殿を造営し、神津嶽から祭神を還した際、神武天皇が神津嶽に手植えをされたという槇柏の木の枝を新しい社殿の前に挿したと伝わる。
樹齢1300年のこの大木は1961年(昭和36年)、第2室戸台風で根腐れを起こし枯れてしまったため伐採し、地上3mを残し保存されている。 |
老女の悲劇の伝説が残る「姥が池」。池は土砂で埋もれていたが、平成23年に整備し、姿がよみがえった。
今から約600年前、一人の老女が生活に困って、神社のご神灯の油を盗んで売っていたが、それが発覚したため、池に身を投げた。その後雨の夜になると青白い炎が現れ、村人を悩ませたと伝える。この物語は井原西鶴の短編話など、多くの俳諧やや戯曲に登場し、「和漢三才図会」や「河内名所鑑」にも取り上げられた、 |
楠木正行ゆかりの井戸。当社に社宝として伝わる『御神徳記』によれば楠木正行が、1349年(正平4年)正月に太刀・物具を献納したとあるが、正行はその1年前の1348年(正平3年)1月の四條縄手の戦いで敗北し、弟正時と差し違え、自害したと伝わっており、1年のずれがある。この時切られた首を洗ったのがこの井戸との伝説もある。 |