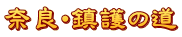神仏霊場のロゴをクリックすれば表紙に、奈良・鎮護の道をクリックすれば奈良霊場の目次に戻ります。
 |
| [参考資料:現地案内板、碑文など] |
|
興福寺にはその歴史の長さから、色々な伝説とともに、その史跡なども今に伝えられており、そのうちの幾つかを紹介したい。 |
 |
 |
 |
| 南大門跡と南円堂の間にある額塚。 興福寺は天平の頃は「月輪山」の山号で、南大門には扁額が掲げられていたが、なぜかしばしば魔障が起こり、風も無いのに樹木が倒れ、水が突然噴出して大穴を開け、石垣を崩壊したので、山内大いに困惑していると、当寺の寺僧の霊夢に「月の字は水に縁ある為なり」とお告げがあった。そこで、額を取り外すと、不思議にその後何も起こらず事なきを得たので、扁額はここに埋められたと伝わる。 |
三重塔の前、芝生の傾斜面に置かれている石は、宝蔵院胤栄の守り本尊「摩利支天石」と伝わる。元は宝蔵院にあったが、寺院は明治初年の廃仏毀釈で取り壊され、この石だけが残されていたのを個人宅に引き取られ、祀られていたが、1999年(平成11年)に100年振りに現在地に戻ってきた。 |
東金堂前に建つ「花之松ノ碑」。 碑文によると、『興福寺花之松は弘法大師のお手植えと伝え、その姿は雄偉で南都一の名木であった。明治・大正の頃には高さ8丈2尺(約24.8m)。幹周囲1丈9尺(5.8m)、枝は東西18間(32.7m)、南北20間(36.4m)も張り出していた。この松も昭和12年(1937年)には枯れてしまった。』という。この碑は名木の復活を願い1940年(昭和15年)に建てられた。 |
 |
 |
 |
| 菩提院に伝わる三作石子詰の伝説。 写真は菩提院の北側入り口(左)、菩提院境内に建てられている三作「供養塔」(中央)。 境内の案内板によると『興福寺の小僧さん達がお堂で習字の勉強していたところに一匹の鹿が入り、小僧さん達の書いた紙をくわえたので、小僧の一人三作が文鎮を鹿に投げた所命中し、鹿はその場で倒死した。当時春日大社鹿は神鹿とされ、「鹿を殺した者には、石詰の刑に処す」との掟があった為、鹿を殺した三作小僧は、子供と云えども許されることなく 三作小僧の年、13歳に因んだ1丈3尺の井戸を掘り、三作と死んだ鹿を抱かせて、石と瓦で生き埋めにされた。(中略) 小僧三作の母親は、「せめて私が生きている間は、線香の一本も供えることが出来るが、私がこの世を去れば三作は鹿殺しの罪人として誰一人香華を供えて下さる方はない。」と思い、紅葉の木を植え、永年供養の花とした。』という悲しい伝説が伝わる。 |
菩提院大御堂。菩提院は奈良時代の高僧玄昉が733年(天平5年)に建立したと伝わるが、むしろ玄昉を弔う一院として造営されたものとの説が有力。 現在の建物は1580年(天正8年)の再建で、堂内には本尊阿弥陀如来像(鎌倉時代:国重文)、不空検索観音菩薩像、稚児観音菩薩像を祀る。 |
|
 |
 |
 |
| 興福寺の放生池として作られた猿沢池は周囲約300m、面積7200㎡。既に奈良時代に築造されていたことが『興福寺流記』に見える。 室町時代から「猿沢池の月」は南都八景の一として、平安貴族の間で、もてはやされたという。 猿沢池七不思議として「澄まず、濁らず、出ず、入らず、蛙はわかず、藻は生えず、魚が七部に水三部」といわれ、この池が赤変すれば凶事の前兆だと言い伝えられ ている。 |
猿沢池のほとりにある采女神社(対岸ビルの右側の赤い箇所)は、帝(平城天皇とも、文武天皇とも伝わる)の寵愛が衰えたことを嘆き悲しんで入水した采女を慰めるために建てられたという。この柳は采女が衣を掛けて入水したと伝わり、衣掛柳と呼ばれている。 | 川路聖謨の「植桜楓之碑」(下段左の写真)の隣に植えられている楊貴妃桜。 寛政三年(1791年)発行の「大和名所図絵」に『昔、興福寺にいた玄宗という名の僧が、この場所にあった桜を大変好んだという逸話から、いつしか人々が、唐の玄宗皇帝が楊貴妃を寵愛した故事に因み、ここの桜を「楊貴妃桜」と呼ぶようになった』という話が紹介されている。 |
 |
 |
 |
| 「五十二段」を上がった左に建つ「植桜楓之碑」。 江戸時代末期に奈良奉行だった川路聖謨が呼びかけ、興福寺や東大寺が中心に、南は白毫寺、西は佐保川堤まで、数千本の桜や楓を植樹した。 この碑は1850年(嘉永3年)3月、聖謨自らが撰文し、多く の植木を寄付した奈良の住民たちの自然観への愛着と配慮を、後世の人には捕植を呼び掛けている。 |
「五十二段」を下りた所に建つ会津八一の歌碑。 興福寺をおもふ 「わぎもこが きぬかけやなぎ みまくほり いけをめぐりぬ かささしながら」 |
興福寺本坊の道を隔てた前に建つ会津八一の歌碑。 猿沢池にて 「はるきぬと いまかもろびと いきかえり ほとけのにはに はなさくらしも」 |