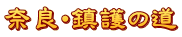神仏霊場のロゴをクリックすれば表紙に、奈良・鎮護の道をクリックすれば奈良霊場の目次に戻ります。
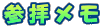 |
| [参考資料:興福寺パンフレット、『奈良・大和の古寺あるき』 実業之日本社] |
|
興福寺は669年(天智天皇8年)藤原鎌足が造立した釈迦三尊像を安置するため、夫人の鏡女王が京山科の私邸に建てた山階寺を始まりとする。672年(天武天皇元年)飛鳥厩坂の地に移し、厩坂寺と称した。 平城京に都が移ると鎌足の子不比等は現在地に金堂を建て、興福寺と寺名を変えた。この創建の年を710年(和銅3年)とする。 |
 |
 |
 |
| 南円堂(国重要文化財)。813年(弘仁4年)の建立。 現在の建物は1789年(寛政元年)頃の再建。西国33所観音霊場の第9番札所。 |
大湯屋(国重要文化財)。現在の建物は五重塔と同時期の再建と見られる。内部には大きな鉄の釜が2基ある。 | 興福寺本坊。興福寺の寺務をとる建物で、表門は天正年間(1573~1592)の建立 。1907年(明治40年)に菩提院北側築地の西方に構えられていた門を移築した。 |
 |
 |
 |
| 2009年(平成21年)9月中金堂の再建工事が始まった。後ろの建屋は仮金堂で、1819年(文政2年)の再建。 この仮金堂は元は薬師寺の金堂を移築した。 |
中金堂の再建工事 2010年12月現在の様子。 | 中金堂の再建工事 2012年1月現在の様子。 新しい中金堂の落慶は2018年(平成30年)の予定。 |
 |
||
 |
 |
 |
| 2009年(平成21年)9月。南大門跡の発掘調査が行われた。 | 2009年(平成21年)9月。発掘された様子。 | 南大門跡2012年(平成24年)3月の様子。 南大門基壇の復元工事が行われている。 |
 |
 |
 |
| 南大門基壇の復元 2012年(平成24年)12月。 発掘調査で出土した基壇の遺構を保護するため、高さ約50㎝の盛り土をし、その上に竜山石や凝灰岩などで基壇が復元された。 復元された基壇は、高さ約1.5m、東西約30.8m、南北約16.6m。 |
興福寺西金堂跡。 734年(天平6年)光明皇后が前年に亡くなった母の橘夫人のために建立。堂宇は1717年(享保2年)に焼失した。 国宝の八部衆像・十大弟子像は西金堂に伝わったもの。 |
西金堂跡の前に建つ「薪能金春発祥地」の碑。 碑文には『薪能は久しく薪猿楽と称し古くは薪咒師猿楽とも称せられ 貞観12年(870年)興福寺 西金堂の修二会が始行せられる…(以下略)。』とあり、現在でも興福寺は毎年5月、観世・金春・金剛・宝生の4流によって薪能が行われている。 |
|
|
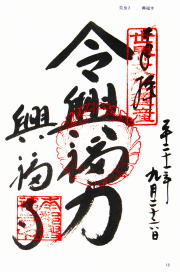 |