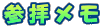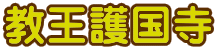|
|
|
 |
 |
 |
| 東寺境内。本坊と金堂・講堂の間に広がる境内は弘法さんの時は出店で埋め尽くされる。 |
勅使門。1936年(昭和9年)弘法大師1100年遠忌の記念事業として、後ろに見える小子坊と共に再建された。 |
慶賀門(国重文)。鎌倉時代前期の創建。東寺の境内北東角、大宮通りに面して建つ。 |
 |
 |
 |
| 西門。慶賀門とは境内を挟んで反対側の北西角、壬生通りに面して建つ。 |
太元堂。大元帥明王と四天王を祀る。北大門を出たところにある。 |
弁天堂。音楽・技芸・財産を司る弁財天を祀る。北大門を出たところにある。 |
 |
 |
 |
| 夜叉堂。夜叉神像は弘法大師の作と伝わる。桃山時代の建立。現在は食堂の前に建っているが、最初は南大門の左右に安置。その後、中門の左右にが、1596年(慶長元年)に中門が崩壊後、現在の場所に移された。 |
天降石。西院毘沙門堂の横にある。石を撫ぜた手で、身体の悪い箇所を撫ぜると病が治ると言われる。江戸時代には護法石(五宝石)、或いは不動石と呼ばれていたが、いつの頃からか天降石と呼ばれるようになった。 |
尊勝陀羅尼碑の亀趺の部分。亀趺の上に載る石碑は碑文の表面の剥離が進み、現在修復中。石碑は元は北野天満宮の宗像社の傍に1853年(嘉永6年)に比叡山の僧願海により建てられが、明治初年の神仏分離令により、この場所に移された。 |
 |
 |
 |
| 八嶋殿。南大門を入って右側に鎮座。この社は東寺以前より鎮座されて入り、鎮座祭神は当寺の地主神とも、大己貴神とも言われる。弘法大師は伽藍建立に先立ち、寺門造立成就、方位安全、法道繁栄を祈願したと伝わる。 |
八幡宮拝殿(上の写真)。八幡宮本殿(右の写真)。796年(延暦15年)の創建。平安京と東寺を守護するため祀られた。1868年(明治元年)に焼失、1991年(平成3年)に123年振りに再建。本尊は弘法大師の作と伝わる僧形八幡神座像と女神座像2躯を祀る。足利尊氏が東寺を本陣としていたとき、鎮守八幡宮の神殿から流鏑(かぶらや)が新田勢に向かって飛び、勝利を収めたとの故事が残る。 |